田舎暮らしの中で、意外と多くの人が見落としがちな家事――それが「草刈り」です。
私の感覚では、移住前と後での認識ギャップが最も大きい作業のひとつ。
都会では雑草を意識する場面は少なく、田園風景の「原っぱ」も、どちらかといえば癒しの景色として映りますよね。
ところが、暮らしてみると一変します。雑草は日々の生活に確実に入り込み、景観や作物、生活動線にまで影響を与えます。
この記事では、私の経験を交えながら、草刈りの現実と向き合う方法、そしてできれば楽しむ工夫までをご紹介します。
- 田舎暮らしを考えているものの、「草刈り」が大変だと聞いて不安に感じている人
- 自然が身近にある生活を望む一方、庭や空き地の維持にかかる負担がイメージできず悩んでいる人
- 草刈りの現実を知り、実際の暮らしをより具体的に想像したい人
- 草刈りにかかる頻度・手間・コストなど、田舎暮らしのリアルな実態
- 負担を軽減するための道具選びや作業の工夫といった、現実的な対処法
- 草刈りとどう付き合うかを通じて、田舎での暮らし方を設計するヒント
草刈りが必要になる場所
暮らしの中で雑草対策が必要な場所は、大きく分けると次の4つです。
- 自宅の庭や家庭菜園
- 自宅そばの空き地
- 生活道路わき
- その他の公共空間(公園・河川敷など)
このうち①は当然「自分の責任」ですが、②~④も生活をしていれば無関係ではいられません。

自宅の庭や家庭菜園の草刈りが必要なのはわかるけど、それ以外は自分にはあまり関係なさそうに感じるなあ。

「自分の土地じゃないのに草刈りなんて…」と思うと、ちょっと気が重くなるかもしれませんが、あくまで地域で気持ちよく暮らすためのちょっとした関わりです。
必要以上に負担に感じることはありませんよ。
1. 自宅の庭や家庭菜園の雑草
春先、小さな芽が出たかなと思っていたら、夏場にはものすごい勢いで雑草が繁茂します。
数日間雨が続いたあとに庭へ出ると、「いつの間にこんなに?」と思うほど背丈を伸ばし、家庭菜園の野菜があっという間に埋もれてしまうこともあります。
雑草は光と養分を奪い、野菜の成長を妨げるため、ピーク時には1〜2週間に一度は対策が必要です。

決して広い面積ではないにしても、毎回、手作業で一つ一つ抜くのは大変だよね。しゃがんだ態勢を続けるのって、思った以上に負担だし、2週間に1度はしんどいな。

そこで活躍するのが「除草鍬」。柄の長いタイプであれば、立ったまま除草作業を行うことが出来ます。
伸びてからの対応にはやや不向きなので、出来るだけ草の芽が出たばかりのタイミングで、小まめに畑や庭の表面を削るように対策すると良いですよ!

出来るだけ早いタイミングでの対策が必要なんだね。
少し広い面積や、草が伸びてきたタイミングで便利な道具はないかな?

その場合は、電動草刈り機を検討しても良いかもしれません。

電動草刈り機!?
それって素人でも大丈夫なの?

確かに本格的な金属刃のものについては、多少の経験がないと危ないかもしれませんね。何より自宅を傷つける恐れもありますし、オーバースペックだと思います。
そこでお勧めなのはナイロンコード刃のものですね。

ナイロンコード刃?

ナイロンの紐のようなものを高速回転させて草を刈る仕組みなので、金属刃よりずっと安心です。
ただし、本格的な除草には向きませんので、その点はあらかじめ割り切りが必要です。

|
【8月30日・9月1日は!枚数限定 最大1,000円OFFクーポン】マキタ makita 18V 充電式草刈機 ナイロンコード 本体のみ MUR193DZ
価格: 12,173円 |
庭の一部では除草剤や防草シート+ウッドチップなどを組み合わせると、作業負担を減らしながら景観も保てます。
植込みの周りや、裏庭など、基本的に立ち入ることの少ない場所であれば、黒い防草シートを敷き詰めた上に、ウッドチップや敷砂利をまくことで、少しお洒落な空間を演出することが出来ます。
ホームセンターなどで材料を買ってくれば、自分でも簡単に施工できますが、1㎡あたり5000円くらいはかかってしまうので、計画的に行う必要があります。
2. 自宅そばの空き地
一見、自分とは関係なさそうですが、放置された空き地は意外に生活に影響します。
不在地主の土地や代替わりで管理されなくなった場所は、夏になると人の背丈を超える草で覆われ、虫や害獣のすみかにもなりかねません。

確かにいくら自宅の庭をきれいにしても、周辺の空き地が草ぼうぼうなのは困るよね。
そういう時はどうすれば良いんだろう?

勝手に刈るのはトラブルのもとになります。まずは近所の方に相談し、所有者と連絡を取るのが筋ですね。
所有者が対応できない場合でも、草刈りのために立ち入る許可だけはもらっておくと安心。
許可を得て刈ったあとの空き地は、風通しや見通しが良くなり、防犯や衛生面でも効果を実感できます。
意外とこの辺、落とし穴になりますので、自宅を購入する際には、周辺の土地の10年後の姿を想像しながら選定することをお勧めします。
3. 生活道路わき
歩道や路肩などの公共用地は自治体が管理してくれると思われがちですが、必ずしもそうではありません。
所有は自治体でも、実際には「利用者が共同で使う土地」という性格が強く、管理も地域住民に委ねられることが多いのです。

所有権が自治体なら、自治体が責任もって管理すべきじゃないの?
都市部の道路は自治体が常に維持管理していると思うけど。

都市部に住んでいるとついついそれが当たり前だと思ってしまいますよね。でも実はそうじゃないんです。
維持管理に必要な経費は、税金から支出されますので、どうしても受益者が限定される場所へは支出しづらいという制限があるんですよね。
そのため、隣接する田畑の所有者が田畑の草刈りのついでに道路脇も刈ったり、自治会で作業日を設けて一斉に草刈りを行ったりします。
作業後は道の見通しが良くなり、歩行者や車の安全にもつながります。
「自分たちが使う場所は自分たちで守る」という当たり前の感覚が、こうした草刈りを支えています。
4. 公共空間(公園・河川敷など)
公園は利用者が多く、自治体の予算で定期的に整備されることが多いですが、河川敷や人通りの少ない場所は後回しにされがちです。
そうした場所の景観維持に欠かせないのが「景観ボランティア」の存在です。
地域の有志が集まり、年に数回の草刈りを実施。作業を進めるごとに、覆い尽くしていた草が減り、川面や景色が開けていく達成感は大きなものです。
自治体や県からわずかに助成が出る場合もありますが、基本は住民の善意と地域への愛着で成り立っています。
ただし、参加者の高齢化で活動が続けられなくなるケースもあり、今後の課題にもなっています。

ボランティアという性質上、どうしても参加者が高齢者に偏ってしまうのが、今後の継続性を考えた場合にもネックですね。
むしろ、有償ボランティアとして、若い人たちがちょっとしたお小遣い稼ぎに参加できる体制にするというのも、返ってWin-Winな関係になるんじゃないかなぁと思っています。
草刈りとどう向き合うか
正直、「草刈りさえなければ…」と思う日もあります。
でも、放置すれば見た目も悪くなり、虫が増え、生活の質が下がるのは確実。
だからこそ、移住を考えている方には、あらかじめ草刈りと向き合う覚悟を持ってほしいと思います。
さらに言えば、「どうすれば少しでも楽しくできるか」を考えてみてください。
なお、どうしても自分で行うのがきつい場合には、シルバー人材センターなどにお願いする方法もあります。比較的安い価格で引き受けてもらえますし、地元の高齢者にとってはちょうどよいお小遣い稼ぎにもなりますので、一つの選択肢と考えてみても良いかもしれませんね。
私なりの草刈りの楽しみ方

最後に私なりの草刈りとの付き合い方をご紹介します。
田舎暮らしの厄介ごとの1つ、草刈りですが、これも田舎暮らしの一部だと思って、前向きに付き合うのがコツですね。
- 子どもと勝負!「どちらが多く抜けるかゲーム」にすると案外盛り上がる。
- 夫婦で雑談しながらのんびり作業。意外と良い運動にもなる。
- 近所の仲良し家族と共同で空き地の草刈りをして、終わったら毎年恒例のバーベキュー。
- 景観ボランティアで新しい知り合いを作る。打ち上げもお楽しみのひとつ。
草刈りは、やらされ仕事だとつらいだけ。でも、自分なりの「楽しむ理由」を見つければ、田舎暮らしの味わい深い一場面に変わります。
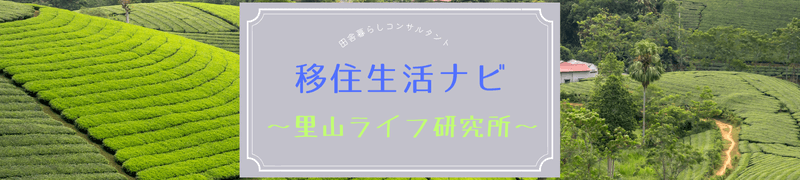





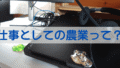
コメント