田舎で子育てってどうなの?―自然の中で育てる暮らしのリアル
【1】自然の中でのびのび育てたいという想い
「子どもを自然豊かな環境でのびのび育てたい」
地方移住を考える理由として、よく聞かれる声のひとつです。
- 虫取りや川遊び、焚き火や畑しごとなど、五感を使った体験
- 走り回れる広い空き地や裏山が遊び場
- 家の中よりも外に出たくなる暮らし
都市部での“管理された子育て”に窮屈さを感じた方には、田舎の子育て環境は魅力的に映るかもしれません。
私自身も、自然の中で遊びながら成長する子どもたちの姿に、「この環境を選んでよかった」と感じることが何度もありました。
ですが一方で、「自然がある=それだけで十分」とも言い切れないのが現実です。
田舎の子育てには、地域ならではのメリットと、向き合うべき課題の両方があります。
【2】田舎だからこその良さ
■ 圧倒的な“遊びの自由度”
- 「ボールを使っても怒られない」「虫取り・川遊びOK」な遊び場が身近
- 小学校のグラウンドや体育館などの公共施設が、土日自由解放されていることも多い
- 教育委員会などが主催する、参加しやすい子供向けイベントも意外と多い
■ 人との距離が近い安心感
- ご近所の方が顔を覚えていてくれて、登下校や外遊びを気にかけてくれる
- 子ども同士のつながりが学年を越えて生まれやすい
- 小規模校では先生との距離が近く、親身な対応を受けやすい
■ 教育の“機会”が広がる場面も
- 地域活動や自然体験学習が豊富に組み込まれている学校も
- 子どもの得意なことを地域全体で応援してくれる雰囲気
- ICT導入が進んでいる学校も増えてきている
田舎の学校では、人数が少ない分、「個を見る」姿勢が強く、子どもが“自分らしく”育つ環境が整っていると感じる場面も多いです。
【3】一方で考えておきたい現実
■ 教育資源の少なさ
- 塾・習い事の数が限られる(通うには送迎が必須)
- 専門的な学習支援や進路指導の機会が都市に比べて少ない場合も
- 小中学校は徒歩圏内でも、高校以降は“通学圏外”になることも多い
■ 進学・就職の選択肢
- 地元に高校が1校しかない/通学に1時間以上かかる地域も
- 大学進学時には親元を離れるケースが一般的(経済的負担も)
- 地元就職も限られた職種に偏りがちで、進路の自由度はやや制限されがち
■ 子ども自体の数が少ない
- 近くに遊ぶ環境はあっても、近所に遊び相手がいない
- PTAや子供会、スポ少などでは、数年ごとに役職が回ってくる
- 幼稚園から中学校まで常に同じメンバーで、良くも悪くも狭い人間関係に
このように、「自然=万能」ではなく、田舎ならではの子育て課題にも備えておくことが大切です。
【4】田舎で子育てを楽しむための工夫と視点
田舎での子育ては、“あるものを活かす”“ないものを工夫する”が基本です。
■ 習い事は“質より量”ではなく“目的ベース”で選ぶ
- 数が少ない分、子どもにしっかり向き合ってくれることが多いにで、その子に合った習い事を
- プラスアルファの勉強なら、通信教育も選択肢の一つ
- 最近は地元の大学生や地域おこし協力隊による”放課後塾”などの取り組みも
■ 親自身のコミュニティづくり
- 幼稚園や学校での親同士のつながりを活かした情報交換は自然と活発に
- 子供会や習い事などに積極的に参加することで、自然と親同士のつながりも広がります
- 自治会・区会などに顔を出すことで、少し上の世代の方たちと知り合っておくのも
■ 早いうちから”子どもの将来”をイメージしておく
- 高校以降の選択肢(通学方法/寮生活・下宿/通信制など)を早めに調べておく
- 子どもの希望(大学進学/専門学校/地元就職/起業など)をしっかり見極めた選択肢を
- 都市部の物まねはNG/都市部に進学したときに、”田舎ならではの体験”が強みに出来る経験を
【5】まとめ ―「どこで育てるか」より、「どう育てるか」
田舎での子育てには、確かに不便さや悩みもあります。
でも、子どもの日々の表情や、地域に見守られる安心感、自然との関わりから学ぶ姿を見ると、得られるものの大きさを感じます。
- のびのび育つだけでなく、社会性や創造性が養われる場面も多い
- 都市では得られない“生きた経験”が、子どもにとっての財産になる
- 家族全体が「どう暮らしたいか」で考えると、子育ての軸がぶれにくい
このブログでは、今後も
- 田舎の保育園・小中学校事情
- 地域の子育て支援制度の使い方
- 「田舎×高校進学」のリアルな選択肢
など、移住×子育ての視点から役立つ情報を発信していきます。
「自然の中で子育てしたいけれど、不安もある…」という方こそ、じっくり情報を集めながら、自分たちのスタイルを考えてみてはいかがでしょうか。
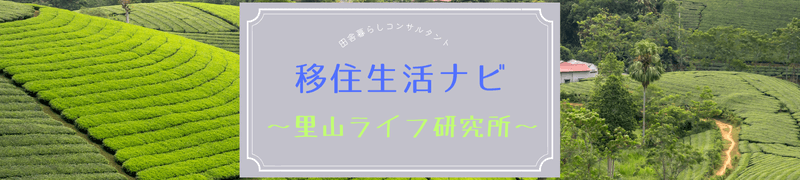

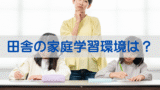



コメント