はじめに:活動費に関心がある協力隊の方へ
地域おこし協力隊の予算は(令和6年度)一人あたり上限520万円。そのうち活動費は200万円です。制度が広がるにつれて金額は増えてきましたが、現場からは「使いづらい」「年度末に残ってしまう」といった声がよく聞かれます。

協力隊としての活動自体は自由度が高いんだけど、いざ活動費を使おうとすると、なかなかOKが出ないんだよね。
普段は協力的な担当者が、困ったような表情をするものだから、何か使わせたくない事情でもあるのかなと思ってしまうよ。

確かにそれは良くある悩みかもしれません。
これは決して、役場担当者のやる気の問題ではなくて、自治体予算の仕組み自体が抱える問題でもあるんですよね。
そこをきちんと理解すれば、活動費はもっと使いやすくなりますよ。
活動費の実態を知りたい/上手に使いたいという協力隊の方
- 活動費が使いにくく感じる理由
- 活動費をうまく使うためのコツ
- 役場経験者ならではの実務的なアドバイス
活動費は「自由なお金」に見えて実は仕組みで縛られている
協力隊から見た活動費のイメージ
協力隊の立場からすると、活動費200万円は活動に応じて自由に使えるお金だという認識だと思います。しかし、実際に使ってみると「思ったより動かしにくい」。
決して、役場担当者がケチっているようにも見えないのに、なぜそのようなことが起きるのでしょうか。
その理由は、役場の「予算の作り方と使い方」にあります。
実は、協力隊予算、やむを得ない事情で大きな制約を抱えたまま予算化されていることが多いのです。
なぜ“大きな制約を抱えざるを得ない”のか
協力隊予算が制約を抱える最も大きな理由は、自治体の当初予算が前年度の秋〜冬にかけて作られるということです。

ちょっと待って。
自治体の当初予算が議会で審議されるのは、通常、2~3月頃じゃなかったっけ?

そうですね。議会で審議されるのはその時期ですが、そこに諮られる「予算案」についてはもっと早い時期に議論されているんですよ。
当然ですが、この時点で翌年度の協力隊の具体的な活動計画が固まっているケースはまれです。特に翌年度着任予定という協力隊の場合、まだ採用自体が決まっていないケースもあり、自治体担当者は手探りで予算編成を行わざるを得ません。
たとえそのようなケースでも、自治体予算は「科目」という”使い道の箱”に割り振ることが求められています。例えば、以下のようなものがあります。
- 需用費(資材や消耗品)
- 印刷製本費(チラシや報告書)
- 委託料(外部への業務依頼)
- 使用料及び賃借料(会場・車・PCのレンタル)
つまり、自治体担当者は半年以上先のことを想像して、活動費全額をこうした枠に仮置きして固定しておかざるをえないのです。
つまり、不確実な未来を“固定”して決める必要がある。ここに活動費が自由に見えて自由ではない理由があります。
執行段階のすれ違い:双方とも“正しい”のに噛み合わない

なるほど。協力隊活動費は、知らないところで支出可能な費目が決まってしまっているということだね。
でも、仮置きなら、ある程度自由は利くんじゃないの?

そうもいかないのが、役場予算というやつですね。
その点についての”すれ違い”についても見ていきましょう。
役場の前提:議会で決まった枠とルールで使う
仮置きとはいえ、予算の枠は、議会によって決定されるものです。
ですから、役場はその枠とルールに従ってお金を執行しなくてはいけません。
一見すると「役場は杓子定規で融通が利かない」と感じられるかもしれませんが、これは役場の思考停止ではなく、住民の意思を反映した議会決定をきちんと実行する責務です。
予算編成上の都合はさておき、一度、議会での審議を経た以上、協力隊の活動費は、事前に決まった枠組みに沿って使われなければいけないのです。
協力隊の現実:活動はリアルタイムで変わる
一方で協力隊の活動は、地域の状況に応じて変わります。
「来月にイベントが決まった」「すぐに試作をしてみたい」など、柔軟に動きたい場面が多いでしょう。
当然、そのような場面で機動的に活用できるのが活動費であって欲しいというのが協力隊の本音だと思います。
そのような柔軟さを台無しにしてしまうような予算のあり方自体、税金の効率的な利用という観点からも問題なのではないかと感じてしまっても不思議ではありません。
実は役場も常に柔軟性を確保しようとしている
ただし、こうした「リアルタイムの変化」への対応は協力隊だけでなく、通常の役場業務でも日常的に起こります。そのため職員も、以下のような工夫をすることで、そのすれ違いを解消するべく、日々の業務に臨んでいます。
- あらかじめ、需用費など使い勝手のよい科目を厚めに計上しておく
- 支出科目が問題となる予算は、予算科目に合わせた契約に出来るよう、あらかじめ支出内容を整理・調整しておく
- 予算の付け替えが可能な補正予算や流用のタイミングを見据えて、支出計画の見直しを行う

これだけ聞くと「ちょっと難しそう・・・」と感じるかもしれませんが、このことを踏まえて、協力隊の立場で知っておくことをまとめておきますね。
どう動かす?:予算流用・専決処分・補正予算の違いと使い分け
予算の「枠」を動かす、3つの代表的な方法
- 予算流用
あらかじめ議会で決まった予算の「大きな枠組み」を変えずに、同じ部局内でお金の配分を付け替える方法です。担当課の判断で処理できることが多く、素早く対応できる仕組みです。 - 専決処分
災害や緊急の事情で議会を待てないときに、首長(市長や町長など)が先に決定・実行し、その後で議会に報告し承認を求める特別な方法です。 - 補正予算
一度決まった予算を見直し、追加や変更を行う正式な手続きです。新しい事業を始めるときや予算の不足を補うときなどに使われます。
議会での審議・決定が必要なため確実ですが、どうしても時間がかかります。

ちょっと難しい言葉かもしれませんが、少なくとも協力隊予算に関連する「予算流用」、「補正予算」の2つについては、しっかり理解しておきましょう。「専決処分」は例外的な手段なので、あまりお目にかかる機会はないと思います。
モデルケース:予算変更が必要となる代表パターン

実例を挙げながら、これらの手段が活用される場面についてみてみましょう。
ただし、このあたりのルールは、市町村による違いがあります。予算科目の整理の仕方から処理の仕方まで、細かい違いはたくさんありますので、あくまでイメージを掴む目的で読んでくださいね。
たとえば、当初予算で地域おこし協力隊の活動費として「消耗品費 500,000円」を計上していたとします。
ところが実際に活動してみると、消耗品は200,000円あれば十分で、残りの300,000円を別のことに回したい…そんな場面を想像してみましょう。
①イベント用のチラシを作りたいと考えた場合
イベントのチラシを印刷するには「印刷製本費」という予算が必要です。
この「印刷製本費」と「消耗品費」は同じグループ(=需用費という節)の中の仲間同士。
だから、この場合は節内流用という手続きで予算を付け替えることが出来ます。
処理は軽めで、課内決裁などで済むことが多いため、担当者も比較的気軽に対応してくれるパターンだと思ってください。
②イベントの講師を呼ぶ費用の増額に充てたい
折角だから、イベント講師を呼ぶための予算を増やして、より良いイベントにしたいなどと考えることもありますよね。
イベントに講師を呼ぶための謝礼は「報償費」に計上されますが、この「報償費」、「消耗品費」は違うグループ(節)に属するため、これは節間流用という手続きが必要となってきます。
この場合、多くの市町村で財政課などとの協議が必要になりますので、担当者の負担もぐっと高まります。
③新たにイベントの講師を呼ぶ予算を作りたい
上記は「増額」のパターンでしたが、元々予定されていなかったイベント講師を呼ぶ予算を作る場合はどうでしょうか。
この場合は、新しい予算の追加になりますので、「流用」ではなく、「補正予算」による対応が必要になる場合が多いです。この手続きは、議会を決定を必要とするため、準備も時間も相当に必要となります。担当者が頭を抱えるのもわかる気がしますね。

どれも当たり前にありそうなパターンだけど、手続きが全然異なっているとはね・・・。
協力隊の立場からすると、①も②も③も同じようなパターンに思えるけど、役場の立場からは全然違って見えるんだね。
活動費を有効に活用するためのポイント(協力隊がやること)
1) 着任直後:活動費の「中身」を知る
担当者に、予算化されている活動費の総額とその内訳を確認しましょう。
予算の内訳を確認する際は、「節」と「細節」を教えてもらいましょう。以下のような表にまとめておくだけで、どのお金はすぐ使えるのか、どのような場合に時間を要するのかが分かるようになりますので、活動計画が立てやすくなります。
| 節 | 細節 | 金額 |
| 需用費 | 消耗品費 | XXXXX円 |
| 印刷製本費 | XXXXX円 | |
| 報償費 | 報奨金 | XXXXX円 |
2) 年間のやりたいことを“ざっくり計画”にまとめる
四半期単位で「いつ・何をやりたいか」「どのくらいかかりそうか」を書き出しておくことも大切です。この場合の金額は概算で十分。
このとき大切なのは「予算化されていない活動費の有無」を確認することです。もし、支出したいけど予算化されていないお金が見つかった場合は、早めに担当者に相談しましょう。

四半期単位というのは、一般的な市町村の補正予算のタイミングになります。不確実な予定でも構わないので、この時期に「補正が発生するかも」と伝えておくことで、担当者も気に留めてくれるようになると思います。
3) 相談は“逆算スケジュール+具体性”
協力隊の活動費は、役場の支出して取り扱われます。
そのため、役場の発注に従った手続きが必要となりますので、今日の明日、という支払いは難しいということを知っておきましょう。予算科目により、手続きにかかる時間も異なりますので、出来るだけ早めに伝えておくことをお勧めします。

イベント企画のスケジュールに「支出の役場相談」を必ず組み込んでおくようにしましょう。逆算スケジュールが大切です。
なお、相談に際しては「○月にXXXのための支出が○万円程度発生しそう」とできるだけ具体的に伝えるのがポイントです。支出科目や見積もりの必要性の判断などは担当者に任せて大丈夫です。
4) 年度途中の見直しは“補正予算の時期”を意識
自治体は四半期ごとに補正予算を組むことが多いので、そのタイミングを意識して相談しましょう。
自分でも残額をメモしながら、補正予算の時期に「追加で必要なもの」を伝えると、予算を組み替えてもらいやすくなります。
5) よくあるつまずき—避けたいNG集
- 直前に相談 → 融通が利かずチャンスを逃す
- 予算確保前に発注 → 活動費は公金。予算が確保できていない段階での発注は絶対にNGです。
- 私費立替で事後精算 → 役場は原則、立替清算できません。やってはいけません。
- 目的だけ伝えて使途が不明確 → 「イベントをやりたい」では動けません。「イベント資材にXXX円、チラシ作成にXXX円」と具体的に伝える必要があります。
- 相談の仕方がわからない → 着任時に説明がないことも多いので、早めに確認しましょう。
- コミュニケーション不足 → 活動費は自由に見えても公金です。担当者が説明責任を果たせる形で伝えることが重要です。
まとめ:活動費は“使える資源”に変えられる
- 編成段階では、不確実な未来を見込んで科目ごとに固定して予算を作らざるを得ません。
- 執行段階では、議会で決まった枠とルールに従って処理するのが役場の責務です。
- 組み替えの方法には予算流用・専決処分・補正予算があります。
つまり、早めの相談こそが、活動費を活かすためのカギです。
今日からできることは、①活動費の内訳を確認、②ざっくり年間計画を作成、③具体的に相談すること。
それだけで、活動費は「使えないお金」から、地域の挑戦を後押しする資源に変わります。
付録:相談文のミニテンプレ
件名:〇月実施予定の〇〇について(活動費の相談)
本文:
・やりたいこと/目的:〇〇(地域の△△のため)
・実施予定:〇/〇(見込み)
・場所・規模:□□
・概算費用:〜〇〇万円(発注候補先:〇社、関連資料添付可)
・相談したいこと:
― この内容に使える予算の妥当性
― 予算が確保できる見込み時期(発注可能なタイミング)
― 発注事務の役割分担(見積・契約・支払など)
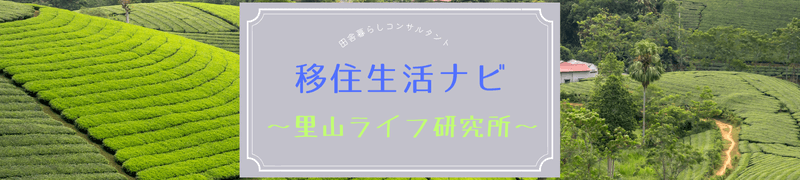
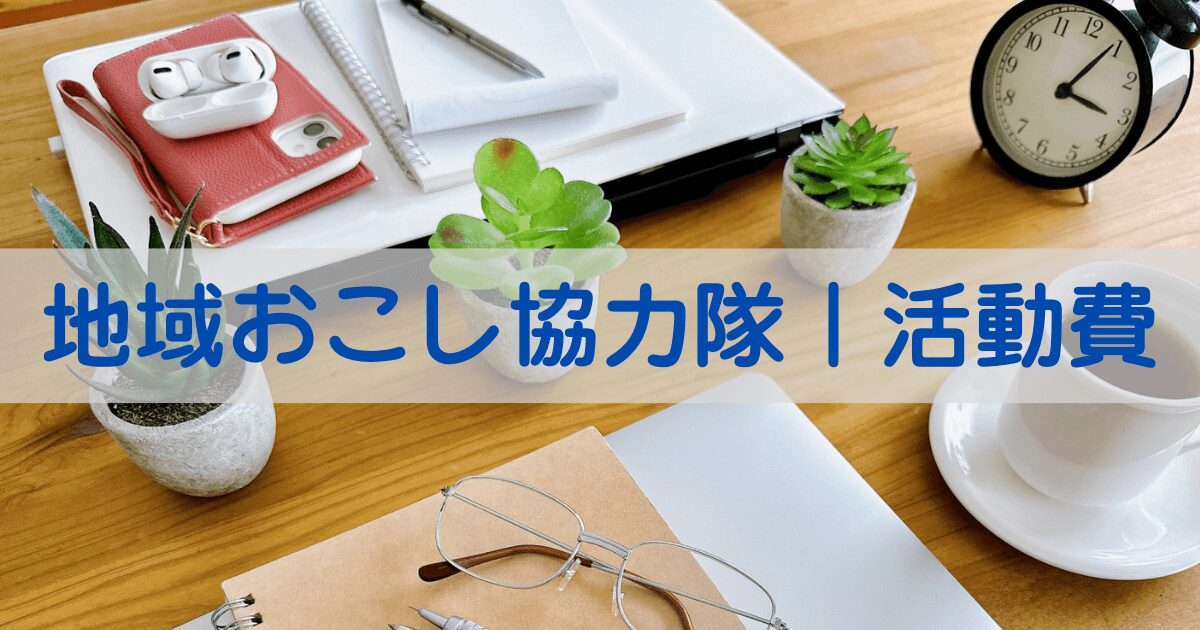



コメント