へずまりゅう奈良市議の「給与明細公開」は、なぜバズった?
「迷惑系ユーチューバーが地方議員に当選」——。
このニュースに、驚きや違和感を覚えた人は少なくなかったでしょう。
「話題づくりでは」「地方議員なんて何をしているのか分からない」といった声も、多く見られました。
そんな中で、へずまりゅう氏が自らの給与明細をSNSで公開したことが注目を集めました。
特に過激な発言をしたわけではありません。
ただ一枚の明細書が、多くの人に共有され、議論を呼びました。
背景には、単なる好奇心や批判とは異なる要素があったように思います。
「地方議員の仕事とは」「この金額で暮らせるのか」——。
その“数字のリアル”が、人々に自分の生活との接点を意識させたのではないでしょうか。
この出来事が示しているのは、政治を語るうえでの新しい入り口です。
つまり、数字のインパクトと“自分ごと化”のしやすさが、地方議員という「意外な選択肢」について現実的に考えるきっかけを与えてくれた出来事と言えるのではないでしょうか。

この記事をきっかけに、地方議員を目指すのもひとつの選択肢なのかもしれないって思うようになったんですよね。
これまで“遠い存在”のように感じていたけれど、具体的な数字や事例を見ると急に現実味が出てきますね。

そうなんですよね。地方議員って、話題になることはあっても、実際の仕事や待遇がどんなものかはあまり知られていません。
でも、生活の延長線上に「地域に関わる仕事」としての地方議員を置いてみると、少し見え方が変わると思います。
- 地方議員に興味があり、「いつかは挑戦してみたい」と思っている人
- 地方議員なんて自分とは無縁、むしろ関わりたくないと感じていた人
- 地域づくりに関わる具体的な手段を探している人
- 地方議員の報酬や兼業事情など、“リアルな実態”
- 議員の仕事が移住者にとって意外と現実的なキャリアになり得る理由
- 「政治」というより“地域づくりの一形態”として議員を捉える新しい視点
地方議員の報酬はピンキリ:年額1,000万円超から月額20万円台まで
もちろん、すべての地方議員が「高給取り」というわけではありません。
- 東洋経済のランキングによれば、年収1,000万円を超えるのは全国でも上位100自治体程度にとどまります。
- 一方で、市議でも年収500万円未満のところは珍しくなく、町村議会の平均は月額21万円程度という調査結果もあります。
- 福島県矢祭町のように、かつて「日当制(1日3万円)」を導入していた自治体もありました。
つまり、報酬の実態は地域によって大きく異なり、「専業で議員だけで食べていける」ケースは限られるのです。

国会議員とは比べられないと思っていたけど、それでも想像より、ずっと安いわね。
地方議員は兼業が可能
地方議員は「特別職の非常勤公務員」に位置付けられ、原則として兼業が可能です。
役場と直接の取引関係が大きい場合などは制限がありますが、町村議会ではむしろ本業を持つことが一般的。
つまり「議員一本で生活する」のは都市部など一部の自治体に限られ、兼業前提で考える方が現実的といえます。

地方議員が「兼業前提」となってしまうことについての批判もあるようですが、個人的には地方議員だからこそ、兼業をしっかり行うべきだと思っています。
兼業が現実的な理由①:自由な時間を確保しやすい
筆者が住む町村部の例を紹介すると、定例議会は年4回×5日、臨時議会は年5~6回×1日。これに加えて地域行事等への参加がありますが、合わせても年間50日前後の拘束日数に収まります。
もちろん、地域住民との意見交換や勉強、行政チェックに時間を割く必要はありますが、日々フルタイムで拘束される仕事ではないため、自由に使える時間は比較的多いのが実情です。
「その自由時間をすべて議員活動に注ぐべきだ」という声もありますが、兼業を通じて得た経験や知見を議会活動に還元するのもまた一つの形。必ずしも“議員一本槍”が最善とは限りません。
兼業が現実的な理由②:なり手不足が移住者へのチャンスに
もう一つの理由は、なり手不足です。
地方議会では無投票当選や定員割れが相次いでおり、全国の町村議選のうち約4分の1が無投票というデータも出ています。
背景には高齢化や低報酬などがあり、「よそ者だから当選できない」というより、むしろ“外から来た新しい力に期待する”という地域も出てきているようです。
移住者にとっては、地方議員への挑戦は意外と現実的な選択肢なのです。
事例紹介:移住して地方議員になった人たち
実際に、移住を経て議員として活躍している事例もあります。
- 福島県会津美里町:横浜から移住した小柴葉月さんは、27歳で町議に当選。広報委員長として住民アンケートや議会評価を導入し、「開かれた議会づくり」に挑戦しています。(キラットふくしま)
- 長崎県五島市:東京から移住した中西大輔さんは、市議として活動しつつ、ブログで「移住者が地方政治に挑む意義」を発信。DXや若者の政治参加といった新しいテーマを議会に持ち込んでいます。(中西大輔HP)
会津美里町の小柴葉月さんのように、広報委員会主導で“開かれた議会”を設計する動きは、議会参加の心理的障壁を下げますし、中西氏のケースのように、DXや若手政治人材の育成をテーマ化し、“外からの規範”を持ち込めるのは移住者の強みです。
これらの事例は、「移住者だからこそ地域に新しい風を吹き込める」ことを示しています。
まとめ:移住×兼業議員は“現実的なキャリア”
へずまりゅう氏の給与公開は、「地方議員」という職業を自分ごととして考えるきっかけを与えました。
実態を見れば、地方議員は報酬に大きな格差があり、多くは兼業前提です。
しかし、
- 自由な時間を確保しやすい働き方
- なり手不足が移住者へのチャンスを広げていること
この2つの要因から、移住後に議員を兼業するという生き方は十分に現実的です。
さらに、会津美里町や五島市の事例が示すように、移住者は地域に新しい視点とエネルギーを持ち込めます。地域と誠実に向き合う覚悟さえあれば、地方議員は移住後のキャリアとして意外性と実効性を兼ね備えた選択肢になるでしょう。

とはいえ、じゃあ地方議員になるにはどうしたら良いの?というのが、正直な疑問化と思います。
これについては、一言では説明しきれませんが、別の記事で改めて考察できればと思っています。
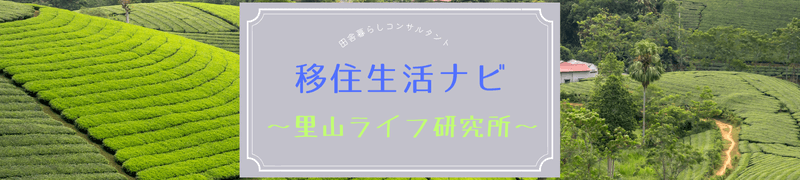



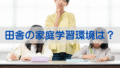
コメント