
地方移住には興味があるけど、そもそも暮らすための家探しってどうすれば良いのか、全くイメージできないんですよね。
ネットの情報だけで理想の古民家を見つけるとか難しいんじゃないかなとか、コネがないと譲ってもらえないんじゃないかとか。。。

確かに人口数千人規模の中山間地ともなると、都市部の不動産市場とは事情も違いますしね。イメージできないのが普通だと思います。
でも、そんな人にこそ、おすすめしたい選択肢があるんですよね。
田舎暮らしと聞くと、「広い土地付きの古民家」を思い浮かべる方が多いでしょう。もちろん、それも魅力的な暮らし方です。ただし、いきなり古民家を購入したり改修したりするのはリスクも伴います。
そこで今回は、地方移住後の住まい選びの中でも意外な選択肢 「アパート暮らし」 に焦点をあて、そのメリットや注意点を整理しました。
- 田舎への移住を考えていて、「まずどんな住まいを選ぶべきか」悩んでいる人
- 古民家や一軒家を前提に考えていて、アパート暮らしを選択肢に入れていない人
- 移住の初期段階で、柔軟に暮らしをスタートさせたい人
- アパート暮らしを含めた、田舎での住まい選びの多様な選択肢
- 生活の自由度・コスト・地域との距離感など、住まいを決める際に押さえておきたい視点
- “理想の家”ではなく、“暮らしやすい環境”を基準に考える住まい選びの考え方
地方移住で選べる住宅の種類
実際に私が暮らす中山間地を例にとっても、「古民家一択」ではなく、さまざまな住まいの選択肢があります。
古民家(一軒家)
築80〜120年といった物件が多く、平屋建てが主流。
外観は古風でも内装はリフォーム済みということもあります。地域の方と親しくなり、家の中を見せてもらうと、意外な快適さに驚かされることも。
比較的新しい一軒家
地元工務店や都市部のハウスメーカーが建てた注文住宅。
二世帯住宅も少なくなく、庭付きでこだわりが感じられる住宅も多いです。建坪は30~50坪程度と平均的な広さですが、町村地域であれば、敷地面積が100坪を超えているというのは普通です。
アパート(賃貸住宅)
「田舎にアパートなんてあるの?」と思う方もいるかもしれませんが、実は中山間地にも点在します。土地活用の一環で建てられることが多く、比較的新しい物件も定期的に登場。単身赴任の先生や若い夫婦などがよく入居しています。
公営住宅
自治体が提供する住宅で、築30年前後の建物が中心。
家賃は低めで、住宅に困っている人の受け皿になっています。アパートと比べても圧倒的に安いですが、入居するには条件があります。古い外観のものが多いですが、内装は定期的に修繕が入っているので、見た目ほどの古さは感じないかもしれません。
地方移住にアパート暮らしをおすすめする理由

折角田舎に移住するのに、アパート暮らしなんて味気ない気がするんだけどなぁ。

その気持ち、わかります。
でも、移住初期の住まいと考えた場合、アパート暮らしには意外と合理的な選択肢なんですよ。
1. 家賃が安くて広い
都市部の賃貸では6畳1Kに月7〜8万円かかるのも珍しくありません。
一方、地方のアパートでは3〜5万円程度で2DK以上の間取りを借りられることも多く、家族でも余裕のある広さが確保できます。
私自身が移住直後に借りたのは、家賃4万5千円・41㎡の2DK。夫婦二人で使っても十分な広さがあり、家具のレイアウトを工夫したり、趣味の作業スペースを持ったりと、暮らしの楽しみが広がりました。
実際の相場を調べたい方は、SUUMOの家賃相場ページ が便利です。エリアや間取りごとの価格帯がわかるので、移住前に具体的な目安がつかめます。
2. 自然豊かな環境を楽しめる
地方のアパートは、窓を開ければ山や田畑が広がる環境にあることが多いです。
私の部屋からは大家さんの畑が見え、その一角を借りて家庭菜園を始めました。春にはイチゴ、夏にはトマトやナスを育て、収穫の喜びを味わえたのは田舎ならではの暮らしです。
「アパート=都市的で無機質」というイメージは、田舎では当てはまりません。自然を身近に感じられる暮らしが待っています。
3. 自治会加入の自由度が高い
一戸建てに比べ、アパートは自治会に入らなくても暮らせる場合が多いです。地域行事に強制的に参加する必要がないため、移住初期は生活の立ち上げに集中できます。
もちろん、慣れてきたら少しずつ地域活動に顔を出せば十分です。
4. 移住先選びの「拠点」になる
地方の中でも、地域ごとに文化や人間関係は大きく異なります。
アパートを拠点にしながら「本当に暮らしたい地域」を探す二段階移住は、失敗しにくい賢い方法です。
気軽に暮らし始められる賃貸アパートは、移住地を見極めるための「試住(お試し住まい)」として最適です。
アパート暮らしの注意点とデメリット
もちろん、アパート暮らしにも注意点はあります。
最大の課題は、人間関係を築く機会が少なくなりがち なこと。自治会に入らないと、地域の行事や人とのつながりが自然には生まれにくいのです。
移住を成功させるには地域との関わりが欠かせませんから、近所のお店で買い物をしたり、地元のイベントに顔を出したりと、自分から動く意識は大切です。
ただし、お子さんがいる家庭では学校や保育園を通じて自然と交流が広がります。アパート暮らしだから孤立する、というわけではありません。むしろ、自分のペースで関係を築ける分、精神的な負担を軽減できるとも言えます。
こんな人にアパート暮らしがおすすめ
- 地域に馴染めるか不安な人
→ 自治会や行事に縛られず、緩やかに地域と関われるスタイルが魅力です。 - 納得する移住先をじっくり探したい人
→ アパートを拠点に周辺を巡る「二段階移住」で、失敗の少ない移住が実現できます。 - 古民家に憧れている人
→ 憧れがあるからこそ、まずはアパートで生活基盤を整え、本当に納得できる古民家を探すのがおすすめです。現地に住んでみて初めて分かることも多いです。
将来的に古民家暮らしを検討するなら、国土交通省の「全国版空き家・空き地バンク」 もチェックしておくと役立ちます。
まとめ|移住初期はアパートが賢い選択肢
地方移住=古民家暮らし、というイメージは強いですが、実際にはアパート暮らしにも大きなメリットがあります。
- 都市部に比べて安くて広い間取りが手に入る
- 自然を身近に感じられる生活が可能
- 一方で、草刈りなどの手間が不要なことも多い
- 自治会加入に縛られず、自分のペースで地域に慣れられる
- 本格的な住まいを探すまでの「試住」として使える
「アパートで始める地方移住」は、妥協ではなく 賢く安全な第一歩。
これから移住を考えている方は、ぜひ選択肢のひとつとして検討してみてください。
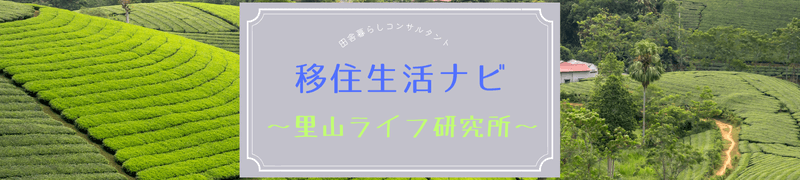






コメント