移住して就農するためのステップを詳しく見ていきましょう
「地方に移住して農業を始めたい」。そう考えたとき、多くの人が最初に直面するのは、「どこから手を付けたらいいのか分からない」という壁です。農業は趣味の家庭菜園とは違い、生活の糧を得る事業であり、地域に根を張って暮らす営みでもあります。だからこそ、順を追った準備が不可欠です。
大切なのは、まず「就農のイメージを作る」こと。イメージを掴んだうえで「具体化」へ進めていくことで、就農の実現性はぐっと高まります。
- 移住を機に農業を始めてみたいと考えている人
- 農地探しや支援制度など、就農までの流れを知りたい人
- 趣味ではなく、仕事として農業に取り組みたい人
- 新規就農の基本ステップと準備の流れ
- 自分に合った就農スタイルを見極めるポイント
- 農地・作物・支援制度など、実際に動き出す前に押さえておきたい基礎知識
イメージ作りのステップ

まずは、「就農する」ということのイメージを掴みましょう。
一口に就農と言っても、そのスタイルは実に様々です。色々なスタイルを知った上で、自分のやりたいことに近い「就農スタイル」をしっかりとイメージすることから始めましょう。
ステップ1:就農スタイルについて知ろう
就農にはいくつかの入口があります。
- 自営就農(独立):自分の農地を借りて経営を始めるスタイル。理想を追える自由さがある一方、初期投資や経営リスクも背負うことになります。
- 雇用就農:農業法人に勤め、給与を得ながら技術を学ぶ方法。生活の安定を保ちつつ経験を積みたい人には安心の道です。
- 研修制度を活用:農業大学校や先輩農家のもとで学び、数年後に独立を目指すルート。研修を通じて「認定新規就農者」への申請もしやすくなります。
- 地域おこし協力隊:生活費が支給され、地域に溶け込みながら農業を体験できる制度。地域との信頼関係を築きやすい点も魅力です。
さらに、農業自体のスタイルにも種類があります。
- 土地集約型農業(稲作・麦作など):広い土地を前提にしたスケール経営。ただし適地は限られます。
- 労働集約型農業(果樹・野菜・花卉のハウス栽培など):面積は小さくても収益を出せるが、手間と労働時間は増えがちです。
この段階では、「どの就農スタイルが自分に合いそうか」「土地型か労働型か」――大まかな方向性を掴むことが第一歩です。
ステップ2:地域の農業傾向を調べる
スタイルをイメージしたら、次は「作物」を考えます。ここでは制度情報は一旦置き、純粋に地域の農業傾向を知ることに集中しましょう。
参考になるのは以下のサイトです:
- 都道府県ごとの農業概要(農水省)
→ 各地域で盛んな作物や特色が一目でわかります。 - 地理的表示(GI)産品登録情報
→ ブランドとして確立された作物がどこにあるのかを把握できます。
ここでの調べ方には二つの切り口があります。
- 作物が未定の人:特産品や気候に合う作物から候補を広げていく。
- 作物が決まっている人:その作物に向いた地域の条件(気候、地形、市場アクセス)を逆算して調べる。
地域特産品を選ぶメリットは大きく、①販路が整っている、②研修機会が豊富、③経営移譲の可能性があるなど、新規参入者にとって学びやすい環境があります。ただし、その分競合も多く参入ハードルが上がる点には注意が必要です。

生産地をしっかりと調べることはとても大切です。
地域内だけの流通を意識するのであれば、ニッチな作物を選択するという考え方もありますが、ある程度広域的な流通を意識するのであれば、生産基盤の整った地域で始めることはメリットが大きいです。
ステップ3:支援情報を整理する
地域と作物のイメージがつかめたら、ようやく支援情報の出番です。
ここで大切なのは、「制度の金額」ではなく「地域を知る機会」に注目すること。
例えば、
- 就農相談会やセミナー:現役農家や行政担当者と直に話せる機会。
- 現地研修や体験プログラム:短期でも地域の生活と農業を一緒に体験できる。
- 移住体験住宅:暮らしと仕事を同時に確認できる貴重な制度。
国の補助金は全国共通のものが多く、地域独自の支援策は「使えたらラッキー」程度。むしろ、現地を知る制度を活用した方が次のステップに直結します。
支援情報を調べるには、以下のページが便利です。
農業をはじめる.JP (全国新規就農相談センター) – 新規就農希望者、農業に興味がある人のための情報を集めたポータルサイト
具体化のステップ

自分の理想とする就農スタイルがイメージ出来たら、それを具体化するのが次のステップです。
イメージがはっきりしている分、具体化するためのポイントもおのずと見えてくると思います。
ステップ4:現地視察で確かめる
机上の情報を超えて、自分の足で歩き、目で見ることが何より大切です。視察の際は次の観点を意識しましょう。
- 気候・地形が作物に適しているか:ハウスの有無や配置も重要なヒント。
- 販路の有無:JAや生産法人による共同出荷体制があるか。既存ルートが整っている作物なら安心感は大きいですが、直販の可能性がある作物なら戦略も変わります。
- 参入の余地:特産品は強みである一方で競争も激しい。「まだ入り込める余白」があるかを見極めましょう。
- 農家の年間暦:単一作物で生計を立てる農家は少なく、複数の作物を組み合わせている場合が多い。その組み合わせも観察ポイントです。
視察で得られるのは単なる風景ではなく、「ここで農業をする自分の姿」を想像できる感覚です。
ステップ5:関係機関に相談する
視察で候補地が見えてきたら、次は具体的に窓口へ。
まずは、その土地の市町村役場を訪れるのが良いですが、市町村を絞り切れていない場合などは、都道府県レベルの営農支援課や農業会議に相談するというのも1つのアプローチです。
- 農業委員会:農地の取得や貸借の可能性を確認する場。
- 役場の農業支援課:制度の詳細、相談会の案内、空き家や移住支援、研修情報など幅広く網羅。まさに「就農の総合窓口」です。
- 都道府県の農業会議:農業委員会の県単位組織の1つですが、新規就農計画の作成支援や資金計画の作成、法人化支援など、市町村では難しいサポートを提供しています。

最初は、行政窓口への相談はハードルが高く感じるかもしれませんが、特段のアポなしでも気軽に相談に乗ってくれるのが行政窓口の特徴です。
最初はちょっとそっけなく感じるかもしれませんが、最終的には親身に相談に乗ってくれると思いますので、思い切って訪問してみることをお勧めします。
ステップ6:自分の計画を形にする
最後に、情報を整理して計画に落とし込みます。
- 栽培作物は何を中心にするか
- 農地と住居をどう確保するか
- 支援制度をどう組み込むか
- 生活費をどう維持するか(雇用就農、副業など)
「認定就農者」として計画が認められると、補助金や融資の優先枠が使えます。ここでの計画は単なる紙の計画書ではなく、未来の農業生活を支える設計図です。
行動チェックリスト
まとめ
移住して就農するという選択肢は、人生の大きな岐路です。焦る必要はありません。イメージを描き、情報を集め、現地を歩き、人と話す。その積み重ねが、あなたの未来を支える農業の形をつくっていきます。
「農業を始める」とは、土地を耕すだけではなく、地域と共に暮らしを耕すこと。その一歩を、ぜひ確実に踏み出してください。
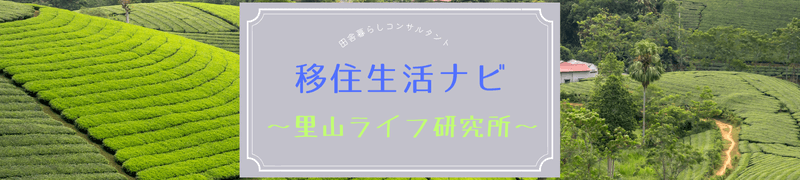


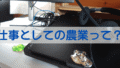
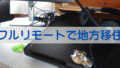
コメント