田舎に移住すると子どもの学習環境はどうなるの?
地方に移住するとき、多くの親御さんが気にするのが「子どもの勉強は大丈夫か」という点です。

田舎に移住したい気持ちはあるけど…子どもの勉強環境が心配で迷ってしまうわ。塾や習い事も少なそうだし、本や教材も手に入りにくいだろうし。子どもの学びにマイナスの影響はないのかしら?

確かに、都会ほど選択肢が豊富なわけではありません。でも今はオンライン学習や教材サービスが整っていて、田舎だからといって勉強面で不利になる時代ではなくなっていますよ。

そうはいっても、やっぱり“いい学習環境”を整えるなら都会の方が有利なんじゃない?

“いい学習環境”をどう捉えるか次第かもしれませんね。成績を伸ばすという点では都会に軍配が上がるかもしれませんが、自然の中でのびのび学べたり、大人とのつながりを通じて社会性を育めたりするのは、田舎ならではの学びの強みだと思います。
- 移住後、子どもの家庭学習をどう整えるか不安な保護者
- 塾や教材の選択肢が少なくても、学びの質を落とさずに支える方法を知りたい人
- 田舎の暮らしを活かしつつ、都会に負けない学び方を作りたい人
- 都会と比べた弱点を補う“家庭学習設計”の考え方(家で伸ばす土台づくり)
- 自然・地域活動など、田舎ならではの経験を“学びの強み”に変える視点
- ツールに頼り切らず、家庭×地域で継続できる学びの仕組み化のヒント
地方の学校教育は本当に不利? 全国学力テストやICT整備から見る実態
都市部と地方では「学力に大きな差があるのでは」と心配されがちですが、実際にはそうとは限りません。義務教育は都道府県単位で提供されており、地域全体で予算や人材が確保されているため、小規模な町や村の学校だからといって学習水準が劣るわけではないのです。
実際、2025年度全国学力・学習状況調査では、秋田・富山・石川・福井といった地方県が東京に引けを取らない好成績を収めています。全体の傾向としても、各都道府県の正答率分布は全国的に大差なく、必ずしも「都市部=有利」という構図ではないことが分かります。

都市部と地方ではもっと学力差があると思っていたけど、意外ね。

そうですね。ただ、やはり都会の方が人口が多い分、有名大学の進学者数が目立ってしまい、“都市部が有利”という印象につながっているのかもしれません。
さらに、学校教育の環境面も全国的に整ってきています。たとえばGIGAスクール構想により、令和4年度末時点で自治体の99.9%が1人1台端末の整備を完了し、全国ほぼ全域でICT環境が均等に行き渡っています。都市部だけが特別に先進的というわけではありません。

また、都会ほど塾文化が浸透していないこともあり、塾を前提としない教育が根付いているなと感じることも多いです。
- 宿題はやや多め
塾に行かない子が多いため、家庭学習を前提に宿題がしっかり出されます。
夏休みや冬休みの宿題も充実していると感じます。 - ICTの積極活用
ICT環境の整備を、教育格差を埋める好機ととらえて積極的に取り組んでいる印象があります。特に遠隔地との交流授業への活用を通じて、田舎ならではの交流機会の少なさを補えているのは心強いですね。
また、首都圏のICT企業が地方教育に積極的に働きかけていることもあり、都会以上のICT環境が整っている学校もあります。 - 検定受検の推奨
漢字検定や数学検定などは、貴重な学ぶ機会として積極的に取り組む子が多いです。学校からも積極的に働きかけを行い、受検費用の一部を助成してくれるケースも見られます。
実際に、全校生徒40人規模の学校からでも県内トップ高校への合格者が出ています。大切なのは地域差ではなく、学び方や本人の意欲次第で十分に道は開けるということです。

田舎だからといって進学をあきらめる必要はまったくありません。むしろ“塾ありき”の都会と違い、本人のやる気をいかに引き出すかが大切になってくるのだと思います。
家庭でできる学習サポート|通信教育・読書・新聞
塾などの環境は整っていませんので、学校だけに任せず、家庭での工夫が学習を大きく左右します。田舎では特に、家庭学習を整えることがポイントです。
1. 通信教育・オンライン学習
Z会、進研ゼミ、スタディサプリ、スマイルゼミ、まなびwith など、通信教育やオンライン教材は選択肢が豊富です。
我が家ではZ会の小学生コースを早い段階から取り入れ、学校の宿題+20分の学習習慣をつけることができました。ただし、教材は子どもの性格や理解度によって向き不向きがあり、兄弟でも違いが出ました。そのため、合わないと思ったら思い切って教材を切り替える柔軟さが大切です。

塾はどうしても送り迎えが必要になってきます。
行きと帰りで二往復するか、送って行ってから帰るまでの時間を有効活用しながら一往復で済ませるかというのは、ちょっとした悩みの種ですね。
2. 読書環境を電子で整える
本屋が少ない地域でも、電子書籍や読み放題サービス(Yomokka!(ヨモッカ)、Yondemy(ヨンデミー)、Kindle Unlimited など)で十分に学習環境を整えられます。
読書に興味がなかった長女も、Yomokka!で出会った小説をきっかけに一気に本好きになりました。今では出かける際に本屋に寄るのが一番の楽しみになっています。「1冊の出会い」が習慣を大きく変える好例です。(とはいえ、次男は全く興味を持ちませんので、やはり個性貼るのかなと思いますが・・・。)

我が家の場合は、Yomokka!が学校タブレットに入っていたのが良かったです。図書館で本を選ぶ感覚で、読みたい本を探せるのが良いみたいです。読書を学びの習慣につなげるYondemyなど、色々なサービスが充実している印象です。
3. 子ども新聞で時事に触れる
読売KODOMO新聞、朝日小学生新聞、毎日小学生新聞は、子どもの時事理解や読解力に役立ちます。我が家では読売KODOMO新聞を購読していますが、大人でも面白い記事が多く、親子で一緒に読んで話題にできています。週1回という無理のないペースも続けやすいポイントです。

子ども新聞は、月当たりワンコイン前後で行動できるのが魅力です。
タブレットやスマホだと、どうしても自分の関心に沿った情報に偏ってしまいますので、このような形で幅広い情報に触れる機会を作っておくことも大切です。
田舎ならではの学習環境の良さを活かす
田舎の学習環境には都会にはない特徴があります。
- 自然や地域活動を通じた体験が豊富
- 勉強漬けにならず、生活の中で学びが広がる
これらは制約ではなく、田舎だからこそ得られる強みです。自然体験が探究心や行動力を育て、勉強と遊びのバランスを取れる環境が学びの幅を広げます。
そしてこの経験は、大学進学後に大きな力を発揮します。
私自身も地方から上京して進学しましたが、自然や地域での経験が都会出身の学生とは違う視点や行動力につながり、差別化できたと感じています。田舎育ちの学びは、長期的には大きなアドバンテージになるのです。
まとめ|心配はいらない。親の理解が学びを支える
「田舎に移住すると子どもの学習環境が不利になるのでは」と不安に思う必要はありません。
都会的な選択肢は少ないものの、通信教育や電子書籍、子ども新聞といった手段は十分に整ってきており、そのギャップを埋められます。
さらに、自然や地域との関わりは、都会では得られない大きな強みです。
結局、子どもの学びを左右するのは環境そのものではなく、親がその環境をどう理解し、どう関わるかです。
田舎の学習環境は「心配するもの」ではなく、子どもの成長に合わせて親子でデザインしていけるチャンス。そう考えれば、田舎移住はむしろ、子どもの学びを豊かにするきっかけになるはずです。
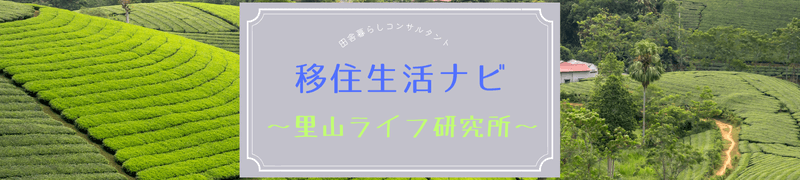

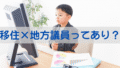

コメント