地方移住を考える上で、多くの方が気になるのが「子どもの学校環境」。
「児童生徒が少ない」という話はよく聞きますが、田舎の学校の特徴はそれだけではありません。
近年では、都会の学校でも少人数化が進んでおり、単に“子どもの数の違い”だけでは、都会と田舎の学校の違いを語れなくなっています。

今回は、私が暮らす中山間地域での実体験をもとに、「田舎の学校事情」をあえて“児童生徒数以外の視点”から掘り下げてみたいと思います。
- 移住を考えていて、子どもの学校環境がどう変わるか不安な親御さん
- 都会と比べたときに、地方の学習環境に遅れや不足があるのではと心配している人
- 教育面の不安を解消しつつ、移住生活を現実的に検討したい人
- 行政マンとして学校教育に関わってきた筆者だから見えてきた、田舎の学校教育の深層
- 学習環境の充実度だけでは見えない、田舎の学校ならではの魅力
- 子どもに提供する学習環境を考えるうえで、視野を広げるきっかけ

田舎出身の人の話を聞いていると、小学校が複式学級だったとか、近くに塾がないから山や川で遊んでいたとか…都会の学校とあまりに印象が違って、不安になるわ。

テレビなんかだと田舎の話は面白おかしく盛られがちなので、そのまま信じる必要はないですが、そうはいっても都市部との違いはやっぱりあるんですよね。
イメージを掴んでもらうためにも、6つの視点から違いを紹介してみましょう。
1. 幼稚園から中学校まで“ずっと同じ顔ぶれ”
田舎では、町内に幼稚園・小学校・中学校がそれぞれ1校しかないという地域も少なくありません。
そのため、子どもたちは多くの場合、幼稚園から中学卒業までの約12年間を、ほぼ同じ顔ぶれで共に過ごすことになります。
メリット
こうした環境の一番の魅力は、友達との絆がとても深まることです。
特に人間関係が大きく変化しやすい中学進学の時期でも、小学校からのつながりがあるため、孤立しにくく、子どもが安心して学校生活を送る土台になります。
さらに町内に1校しかない学校だからこそ、親子で同じ学校に通うケースが非常に多く、親世代が同じ学校の同級生だった、という関係が珍しくありません。
このような形で、「同級生同士」というつながりが、大人になってからも続きやすく、時に一生ものの人間関係へとなりやすいというのは、大きな特徴だと思います。
デメリット
一方で、田舎の学校生活には、次のような面もあります。
まず一つ目は、新しい人間関係を築く機会が乏しいことです。
同じ顔ぶれで長い時間を過ごす安心感はあるものの、新たな人間関係に触れるきっかけが少なく、人脈づくりを学ぶきっかけが乏しいという側面があります。
さらに、人間関係が固定化されやすく、トラブルが起きたときに逃げ場がないと感じる場合があり得ます。
クラス替えや進学でリセットされることが少ない分、息苦しさを覚える場面もあるかもしれません。
ただし、田舎では、学校や教育委員会との距離が近く、また親同士も顔なじみであることが多いのも事実です。問題が起きた際には、第三者をうまく巻き込みながら「どうすれば前向きに解決できるか」を一緒に考えやすい土壌がありますので、そのような関係性をうまく活用していきたいものです。

都会でも小規模校は増えてきましたが、中学への進学を機に、他の小学校に通う新しい同級生が増えるというのが一般的かと思います。
そういった機会が高校進学まで皆無という環境は、やはり子供の成長環境として大きな違いだと思います。
2. 通学はバスが基本。歩く機会が少ない現実
学校の数が少ないということは、当然ながら自宅から学校までの距離も長くなります。
そのため、バス通学が基本になります。専用の通学バスや地域の路線バスを利用することが一般的で、徒歩で通える子どもはごく一部です。

小中学校への通学手段はきちんと整備されているのね。片道何キロも歩いて通わないといけないのかと心配していたけど、毎日送り迎えが必要というわけでもないなら安心だわ。

そうなんです。私も小学校の統合事業に関わったことがありますが、子どもたちの通学手段を確保するのは大きな課題なので、しっかり整えられているケースが多いですね。そこは安心していいと思います。
ただ一方で、バス通学が中心になることで、別の課題も出てくるんです……。
意外に見落とされがちですが、この「バス通学が基本」という点は、田舎の子育てならではの隠れた課題にもつながります。
なぜなら、多くの子どもが通学の中で歩く機会をほとんど持てないからです。
田舎の子どもは自然の中で体を動かして元気いっぱい――そんなイメージがあるかもしれませんが、実際には都市部の子どもよりも歩く距離が圧倒的に少ないという実態があります。結果として、普段から体力や足腰を鍛える機会が限られてしまうのです。
さらに遊びに行くときも「親が車で送迎する」のが基本。日常的な運動量を確保しづらいという点は、親として押さえておきたいポイントです。

これは、子どもだけでなく、親にとっても課題になりがちです。
田舎では意識的に歩く機会を設けないと、運動不足になりがちという点はあらかじめ気にしておきたい点ですね。
3. 若い先生が多く、親しみやすい雰囲気に
田舎の学校には、若い先生が多いという特徴があります。
これは教員の採用や人事配置の仕組みによるもので、公立学校の教員は都道府県単位で採用され、さまざまな地域への配置を経験することになります。
その中で「僻地勤務」と呼ばれる田舎の学校は、若手教員の研修的な意味もあり、独身の若手が配属されやすい傾向があります。
結果として、田舎の学校はフレッシュな先生たちで構成されることが多く、児童生徒との距離が近く、活気ある雰囲気が生まれやすいという良さがあります。
とはいえ、若い先生が中心になることで、教職員全体としての経験値が不足するという面も否めません。

若いやる気のある先生が多い印象です。
親の目線から見ると、やや頼りない部分も見えてしまいますが、一生懸命子供と向き合ってくれる先生は、ほんとありがたいです。
4. ベテランの地元出身教員が頼れる存在に
若手が多い一方で、地元出身のベテラン教員が地域に戻ってくるというパターンもよくあります。
一度都会で経験を積んだ先生が、家庭を持ち、ふるさとに戻ってくる――そんな形で地域に根差して働いている先生がいます。
このようなベテランの存在は、若手教員を支える貴重な存在ですし、学校と地域をつなぐ“橋渡し役”にもなってくれます。
ただ、間に中堅層が少ないために、若手とベテランのギャップが大きくなりがちなのも事実。組織全体としてのバランスという点では、ややアンバランスさが見られるのが、田舎の学校の特徴かもしれません。
5. 教育委員会が身近な存在に
都会に暮らしていると、「教育委員会」と聞いても、あまりピンとこない方が多いのではないでしょうか。
でも田舎では、教育委員会がとても身近な存在です。
地域によっては、町主催の行事や子ども向けイベントの企画・運営を教育委員会の職員が担当することも多く、実際に子どもたちと接する機会もあります。
保護者からしても、「ただのお役所」ではなく、子どもを一緒に育ててくれるパートナーのような感覚で関われることがあります。
また、学校の取り組みに対してもきめ細かく目配りしてくれるため、要望が通りやすかったり、改善のスピードが早かったりといった小回りの利く教育行政が可能になるのも、地方ならではの強みです。

私も2年間、教育委員会で仕事をしていましたが、学校教育にいかにデジタルを取り入れるか、子どもたちが楽しんで地域を学べるイベントは何かなど、ほんと一生懸命考えました。
6. 地域にとっての“おらが学校”
田舎の学校には、子どもたちや保護者だけでなく、地域の人々の想いが深く込められていることがよくあります。
都会では「学校=教育の場」という認識が一般的かもしれませんが、田舎では「学校=地域のシンボル」としての側面が強く、地域住民にとっては“自分たちの学校”という意識、いわゆる“おらが学校”感覚がとても強いのです。
また、こうした“シンボル”としての側面が強いためか、個性的な学校建築もよく見かけます。
最近では地域の特色を反映したモダンなデザインの校舎や、木材をふんだんに使った温かみのある内装が取り入れられることもあり、「この学校で育ってよかった」と思えるような空間づくりがされています。
一方で、昔ながらの木造校舎や昭和レトロな鉄筋校舎など、“時代の味”をそのまま残している学校も数多く存在します。
最新設備とはいかないかもしれませんが、年月を重ねた空間だからこそ醸し出される温かさや記憶が、子どもたちの原風景になっていく――それも田舎の学校の魅力の一つです。
おわりに:学ぶ場ではなく、暮らす場としての学校
ここまで、田舎の学校事情を「人数以外の観点」からご紹介してきました。
読み進める中で、「やっぱり田舎の学校は不便そう…」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
正直なところ“学ぶ環境”という視点だけで比べれば、都会の方が恵まれていると感じる場面は多いです。
しかし、学校を“暮らしの中の一部”として見ると、田舎には都会にない良さがたくさんあることにも気づきます。
たとえば、
- 子どもも親も、地域全体で顔が見える関係性の中で育っていく
- 小さな学校だからこそできる柔軟な取り組み
- 自然と地域に囲まれた安心感のある学びの場
どれも、都会では得がたいものです。
移住を考える際には、ぜひ「何を優先したいのか」を軸に、教育環境を見てみてください。
学力重視なのか、地域との関わりを重視するのか、子どもの性格に合わせて考えるのか――
答えは家庭によって異なりますが、その視点を持つことで、自分たちに合った場所がきっと見つかるはずです。
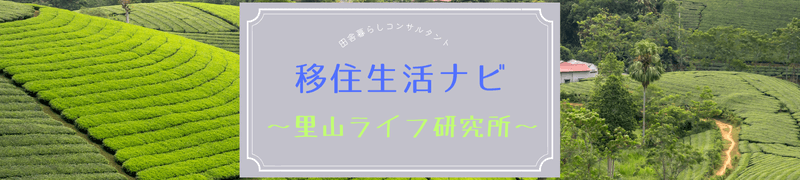

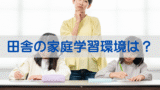

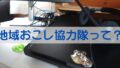
コメント